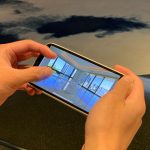物件を貸す場合・借りる場合、「普通借家契約」と「定期借家契約」の違いを理解しておく必要があります。
今回はそれぞれの契約形態の特徴とメリット・デメリットを貸主・借主双方の立場から解説します。
普通借家契約

住居の賃貸借における一般的な契約形態です。
契約期間は1年以上と定められていますが、基本的に2年間とされているケースがほとんどです。
契約満了の際は原則として更新されます。
「貸主(オーナー)よりも借主(入居者)の立場が強い契約」と言われています。
貸主側のメリット・デメリット
メリット
・一般的な契約形態なので借り手が付きやすく、賃料等の条件も相場通りに募集が出せる
・大手法人契約(借り上げ社宅)に対応できる
・定期借家契約に比べ契約自体が簡単(口頭でも契約が成立する)
デメリット
・貸主からの解約(いわゆる追い出し)が非常に難しく、実質不可能に近い
・賃料改定に借主が同意しない場合、基本的に値上げができない
借主側のメリット・デメリット
メリット
・更新を希望すれば原則更新し続けられるため、追い出されるリスクがない
・賃料を一方的に増額される心配がない
デメリット
・定期借家契約に比べ契約時の条件交渉が通りづらい
・更新の際に更新料(一般的に新賃料の1ヶ月分)が掛かる
定期借家契約

あらかじめ定めた契約期間に基づき、確定的に契約が終了する契約形態です。
借主側の保護に重点が置かれている普通借家契約に比べて貸主側のメリットが大きくなります。
契約期間に制限はなく、たとえば「~年~月まで」という設定も可能です。
更新という概念はありませんが、再度契約をし直す「再契約」という形で更新に代えて契約を継続することもできます。
貸主側のメリット・デメリット
メリット
・期間経過後、確実に借主が退去するため売却や自己使用の計画がしやすい
・転勤等で自宅を空けている間のみ貸す、ということが可能
・再契約時に貸主側の裁量で賃料を改定できる
デメリット
・通常、普通借家契約よりも借り手が付きづらく、賃料を相場よりも低くするなど工夫が必要
・大手法人契約(借り上げ社宅)に対応できない
・普通借家契約に比べて契約自体が煩雑
借主側のメリット・デメリット
メリット
・普通借家契約よりも安い賃料で借りられることが多い
・更新料がない(再契約料が掛かる場合あり)
・初期費用が普通借家契約よりも抑えられることも
デメリット
・貸主から再契約を断られる可能がある
・再契約時、賃料を一方的に改定されても対抗できない(再契約する場合)
・途中解約する場合に定められた期間に満たない分の賃料相当の違約金が発生する場合がある

いかがでしょうか。
どちらが良い・悪いというものではありませんが、端的に言えば普通借家契約では立場が「貸主<借主」に、対して定期借家契約では「貸主>借主」になる場面が多くなります。
たとえば普通借家契約を締結したものの借主に問題があり、賃料をしばしば滞納したり近隣トラブルを起こすような方だったとしても追い出すのは容易ではありません。借主が更新を希望する場合、嫌でも契約は更新されてしまいます。
ですが定期借家契約では借主側が不利であることから当然に借り手が付きづらくなり、早期に空室を埋めることが難しくなります。
「なるべく自分が有利な契約を結びたい」と思うのは当然の心理ですが、片方が有利になりすぎても契約はうまく運びませんしトラブルの原因にもなり得ます。
たとえば定期借家契約であっても契約期間を長く(3年以上)設定したり、賃料や礼金を下げるなど、なるべくお互いのメリット・デメリットが釣り合う契約を心がけることが肝要です。
リテラ株式会社 代表取締役 加藤 圭一郎
最新記事 by リテラ株式会社 代表取締役 加藤 圭一郎 (全て見る)
- おとり物件の見分け方は?特徴と騙されないための対策を解説 - 2023年10月6日
- 勝どき駅の住みやすさは?周辺環境や家賃相場をご紹介! - 2022年8月2日
- 更新!2023年再開発が進む街!豊洲に住む魅力とは - 2022年5月12日
- 人形町駅の住みやすさは?周辺環境や知っておきたいことを徹底解説! - 2022年4月28日
- 事故物件とは?見分け方を不動産のプロが解説 - 2022年4月28日